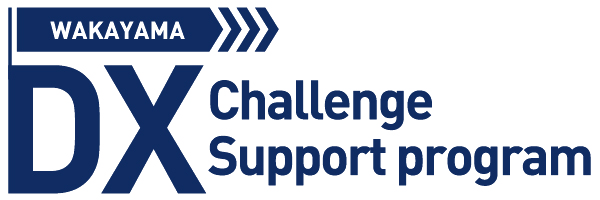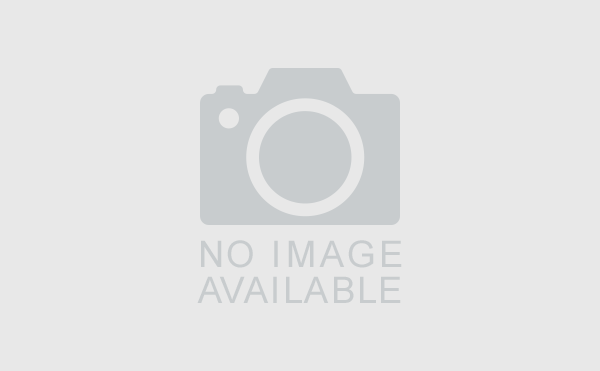株式会社リカーショップゴワ様-中間報告インタビュー
リカーショップゴワ プロジェクト関係者の皆様
・自己紹介と事業の説明をお願いします。
後和直樹と申します。和歌山市で生まれ育ち、2010年に大学を卒業後、札幌と東京で4年間卸売業界に従事しました。2014年に地元の和歌山に戻り、株式会社リカーショップゴワに入社しました。配達や営業を通じて新規開業のオーナー支援を行う中で、「飲食店の成功を全力で後押ししたい」という思いを抱くようになり、現在は専務取締役として取り組んでいます。
弊社は1924年に創業し、和歌山市を拠点に業務用の酒類食品や消耗品を主に飲食店向けに卸販売しています。「お酒を持ってきてほしい」というニーズから40年前に業務用配達を開始し、今では多様なニーズに応えられる体制を整えています。
・御社はどのような業種で、どのような特色や強みを持っていますか?
弊社は酒類食品卸売業を中心に業務用酒販店として商品のお届けだけでなく、飲食店の開業支援や運営支援にも取り組んでいます。LINEを活用したオンライン注文システムを自社開発し、店舗様が簡単に商品を発注できる仕組みを提供することで、業務効率化を支援しています。
永くご繁盛されている飲食店の特徴に、理念やコンセプトが明確であることが挙げられます。新規開業時には、コンセプトの明確化を通じた長期的な成功のサポートを行っています。また、人手不足に対応するため、DX推進としてレジや予約システム、モバイルオーダーなどの導入を提案。例えば「大•メガジョッキ」の導入提案もスタッフの負担軽減や効率化に役立っています。
居酒屋業界ではオペレーション変更を嫌う傾向がありますが、具体的なデータを示し納得いただける提案を心がけています。
専務取締役 プロジェクト責任者 後和 直樹氏(右)
・なぜこのプログラムに参加することに決めたのですか?
私たちの業界は、超労働集約型で斜陽産業、さらに超アナログな業界です。DXやデジタル化とは程遠い「努力・気合・根性」が重視される世界で、課題が山積みの状態でした。そんな中でも、「自分たちにできることから始めよう」と考え、改善に取り組んできました。
このプログラムに参加を決めたのは、現在進めている業務改善をさらに一段階進めたいという思いからです。特に、業務改善の自社事例を通じて飲食店へのサポートを進められるようになることを期待しています。
・本プログラムの中間地点を迎えて、どのような変化がありましたか?
これまで漠然としていた課題に対し、具体的な方向性が整理され、取り組み方が明確になった点が大きな変化です。紙のチェックシートをAppSheetでデジタル化する見通しが立ち、業務効率化に一歩近づけました。また、Googleツールの活用ノウハウを得たことも、業務改善の具体的な方法を見出す成果となりました。
また、私はツール導入は最終段階であり、その前に「不の業務」や「無駄な業務」を整理することが重要だと考えています。課題発見シートを使い、「ムリ・ムダ・ムラ」の視点で業務を見直す方法が特に有効でした。このフレームワークにより、見えていなかった課題を発見し、改善点を明確化できました。
・現在進めているDX推進から、新しいビジネス機会や可能性はありますか?
私たちが業務改善に取り組む目的は、単に売上を上げることではなく、業務の標準化や繰り返し行われる業務の自動化を進めることで効率化を図ることです。様々な取り組みにより、顧客とのコミュニケーションを深め、付加価値の高い提案やサービスの提供を実現し、全体の顧客満足度を向上させることを目指しています。
・本プログラムの参加メンバー、および関係者は、本プログラムを通してどのような変化がありましたか?
【中尾様】所属:管理部
DX化によって業務の標準化が進み、スキルや経験に依存していたタスクが減少し、効率化が進んでいます。一方で、タスクの多様性やイレギュラー対応といった課題は依然として残っており、試行錯誤が続いています。それでも、業務フローの見直しを通じてムダやムラが改善され、新たな課題を発見するきっかけとなっています。
さらに、「業務をシンプルにする」という意識が現場に浸透し、理解が深まるとともに改善の推進にも繋がっていると感じています。
管理部 中尾氏(右)
【末松様】所属:営業部
DXの推進により業務の整理が進み、新たな課題や改善点が明らかになりました。例えば、配達員が携帯端末でマニュアルにアクセスできるようになり、会社に戻る手間が省け、顧客対応の時間が増えています。ただし、デジタルに不慣れな人には操作が難しい点が課題として残っています。誰でも使いやすい仕組みを整えることで、DXの目的達成に繋がると考えています。
リカーショップゴワ 専務取締役 プロジェクト責任者 後和 直樹氏(中央)、管理部 中尾氏(左)、営業部 末松氏(左から3番目)
・プロジェクトを通して今後採用する人材像に感じ方や変化はありましたか?
世の中は常に変わっていきますが、その中で幹部が行動や変革の背景となる要点をしっかり押さえ、それを全員で認識合わせをすることが重要です。この認識が共有されることで、経営層はワンチームで効率的に動けるようになり、現場のマネジメントもスムーズになります。一方で、現場にはこうした高い視座を求めるのは酷な場合もあるため、まずは再現性の高い業務に意識を向けてもらい、「実行すれば仕事が楽になる」と実感できる環境を整えることで、生産性の高い良いチームを育成していくことが大切だと考えています。
・本プロジェクトのDX促進において、何か具体的な目標はありますか? またそれを達成できましたか(達成する見込みはありますか)?
本プロジェクトのDX促進における具体的な目標は「お客様との時間を増やすこと」です。そのため、販売メンバーが担当している事務業務を別の人に移管し、業務効率化を図る計画を進めています。特に、現在紙ベースで運用しているチェックリストをデジタル化し、作業時間や効率を数値で見える化することを目指しています。
紙のチェックリストは転記作業に多くの時間を要し、付加価値が少ないため、改善の必要性を強く感じています。デジタル化を進めることで、販売メンバーが事務作業から解放され、顧客とのコミュニケーションや提案に集中できる環境を整えたいと考えています。
また、AppSheetを活用した効率化も目標の一つです。プロジェクトで得た「課題の整理方法」や「ツールの活用ノウハウ」を活かし、残りの期間で具体的な成果を形にしていきたいと思います。
・地方企業の撤退や中小企業の減少に対する解決策として、本プログラムのDX促進は効果的なアプローチだと思いますか?またどんな効果が生まれると考えられるでしょうか?
業務改善において、DXやツールは目的ではなく手段だと考えます。「本当に必要な業務か」を自問し無駄を省く姿勢を社員と共有することで、価値ある仕事に集中できる環境が整いました。ツールの導入を目的化せず、業務改善にどう活用するかを明確にすることが、DX推進の本質だと考えています。
・これからDXの第一歩を踏み出す企業に対して、何かアドバイスをお願いします。
DX推進を進める上で最も重要なのは、「トップが先陣を切ること」だと考えています。中小企業ではトップが率先して理解し、動くことで方向性が共有され、現場も動きやすくなります。また、日常業務の中で「なぜこの業務が必要なのか?」と疑問を持つことも大切です。この問いかけを通じて現場からのフィードバックを得ることができます。慎重で丁寧なコミュニケーションを心がけ、現場の声を吸い上げながら改善策を考えることが重要だと感じています。