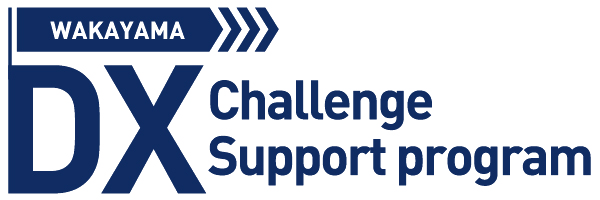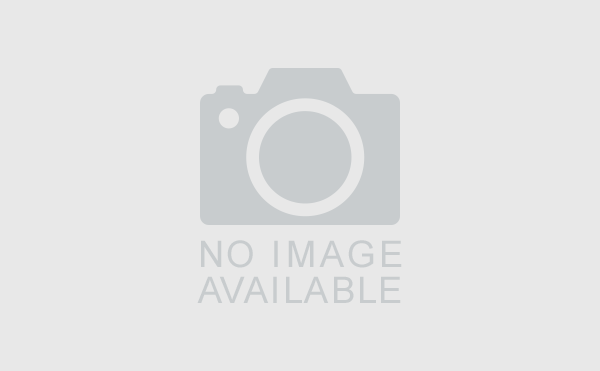有限会社三和金型製作所様-中間報告インタビュー
有限会社三和金型製作所様 インタビュー内容
三和金型製作所 プロジェクト関係者の皆様
自己紹介と事業の説明をお願いします。
有限会社三和金型製作所と申します。 社名に「金型」とついていますが、実は金型そのものの製作はあまり行っていません。主に金型の修理や改造を手がけており、産業用部品の加工が中心業務です。
当社は小規模ながらも、顧客のニーズに柔軟に応えることを大切にしています。どんなに小さな依頼でも丁寧に対応し、「ものづくり」の精神を大切にした仕事を心がけています。
専務取締役 プロジェクト補佐 小嶋一彰氏(写真右側奥)
御社はどのような業種で、どのような特色や強みを持っていますか?
金属加工と聞くと、全自動の省人化された工場をイメージされるかもしれませんが、当社では職人が汎用機を使い、一つひとつ手作業で加工を行っています。この「汎用加工」を大切にしており、職人ならではの技術で対応しています。
汎用機を活用することで、特注品や少量多品種の加工に柔軟に対応できます。また、職人が機械を扱うため、細かな調整や微妙な加工精度の違いにも対応可能です。この点が当社の大きな強みだと考えています。
なぜこのプログラムに参加することに決めたのですか?
DXやITといった言葉は耳にするものの、実際に何をどうすればよいのか分からず手をつけられずにいました。当社は小さな町工場で、紙の管理が業務の要でした。そのため、ペーパーレス化という話を聞いても、「それでは仕事が回らなくなるのでは?」という不安がありました。
そんな中、dToshのセミナーで「本質業務に集中することがDXで実現できる」という言葉を聞き、目から鱗が落ちました。ものづくりにもっと集中できる可能性を追求したいと思い、このプログラムに参加を決めました。
また、デジタル化によって「業務の効率化が図れるのでは」という期待もありましたが、最初はその実現方法が見えませんでした。しかし、セミナーやプログラムの内容を通じて、具体的な手法を学び、これなら挑戦できると感じました。
プログラム参加前に感じていた課題や印象はどのようなものだったでしょうか?
正直、DXは大企業が多額の資金を投じて行うもので、自分たちには無縁だと思っていました。しかし、現在使用しているソフトウェアでも対応可能なことが分かり、ハードルが大きく下がりました。
これまでも他のDXセミナーに参加したことがありましたが、専門用語が多く、具体的なイメージが湧かず行動に移せませんでした。このプログラムでは実践的な内容が多く、取り組みやすさを感じています。
また、「DXには高額な投資が必要」という先入観がありました。しかし、小さな改善からスタートできるということを知り、徐々に挑戦意欲が湧いてきました。
本プログラムの中間地点を迎えて、どのような変化がありましたか?
業務の見える化が進む中で、限られたリソースを最大限活用する重要性を実感しました。また、「小さな変化でもDXと呼んでいいのか?」と考えることもありましたが、小さな一歩の積み重ねこそが重要だと感じるようになりました。
職人の間でも、「うちの工場ってかっこいいよな」と感じる場面が増え、少しずつ意識の変化が見られるのが嬉しいです。最近では、デジタル技術を前向きに捉えるようになり、意欲的に取り組む姿勢が見られるようになりました。
また、デジタル化が進むことで、「業務の負担が軽減できるのではないか」といったポジティブな意見も聞かれるようになり、会社全体の雰囲気も少しずつ変わってきています。
課題を解決するために、どのように工夫されましたか?
職人たちは、デジタルに対する期待と不安を抱えています。負担を増やさず、苦手意識を払拭するため、操作を簡単にする工夫や、少しずつ進められる環境づくりを心がけています。
例えば、操作ボタンの数を減らしたり、簡単なマニュアルを用意したりしています。また、進捗を共有する打ち合わせを頻繁に行い、不安を解消しながら進めています。
さらに、現場の声を積極的に取り入れる仕組みも整備しました。例えば、職人が実際に使うツールについて、どのように改善すればもっと便利になるのかをヒアリングし、その意見を反映させるようにしています。この取り組みは、現場の士気向上にも繋がっています。
また、社内だけでなく外部の専門家とも連携し、最新の知見や技術を取り入れることで、より効率的な解決策を見つけ出しています。
本プログラムの中間地点を迎えて、何か具体的な成果や変化はありましたか?
経営計画の方向性が明確になり、次に進むべき道筋が見えてきました。また、業務プロセスの効率化も進み、従来よりもスムーズに仕事を進められるようになりました。
さらに、リアルタイムで状況を把握できるようになり、顧客満足度の向上も期待しています。これにより、取引先との信頼関係がより強固なものになると考えています。
最近では、従業員全体で業務改善の意識が高まっています。
営業・企画広報部長 プロジェクト責任者 山本知香氏(写真右側手前)
・本プロジェクトのDX促進において、何か具体的な目標はありますか?
5年後、10年後に安心して働ける会社を目指しています。無駄な残業を減らし、効率的な作業環境を整えることで、働きやすい職場を作りたいです。
短期目標としては、タスク管理を共有し、職人同士で協力しやすい環境を整えることを挙げています。この仕組みが実現すれば、さらに働きやすくなると考えています。
さらに、バックオフィスの効率化を進めることで、営業活動にも注力できる時間が増えると期待しています。このような形で全社的な改善を進め、持続可能な成長を目指していきます。
これからDXを始めようとしている企業に対して、アドバイスをお願いします。
「どうなりたいか」を明確に描き、そのために必要な行動を考えることが重要です。目的を見失わず、柔軟に計画を調整しながら進めていくことがDX推進の成功につながると感じています。
「うちができたらどこでもできる」と思っています。全員合わせても少人数の会社でも十分に可能です。大規模な投資をせずとも、小さな一歩から始めることで効果を感じられるはずです。
具体的には、現場の負担を減らすことを第一に考えながら進めると良いと思います。システム導入だけではなく、現場とのコミュニケーションを重視し、みんなが納得して進められる体制を整えることが成功の鍵だと実感しています。ぜひ、一歩を踏み出してみてください。
また、DXは単なる業務改善だけでなく、企業文化や働き方そのものを変える可能性を秘めています。これを機会に、会社全体のあり方を見直すきっかけとして取り組むと良い結果に繋がると思います。
三和金型製作所 プロジェクト関係者の皆様